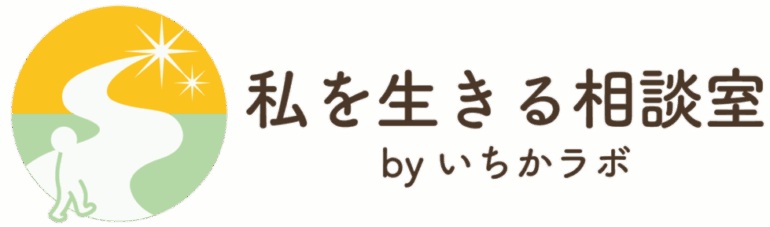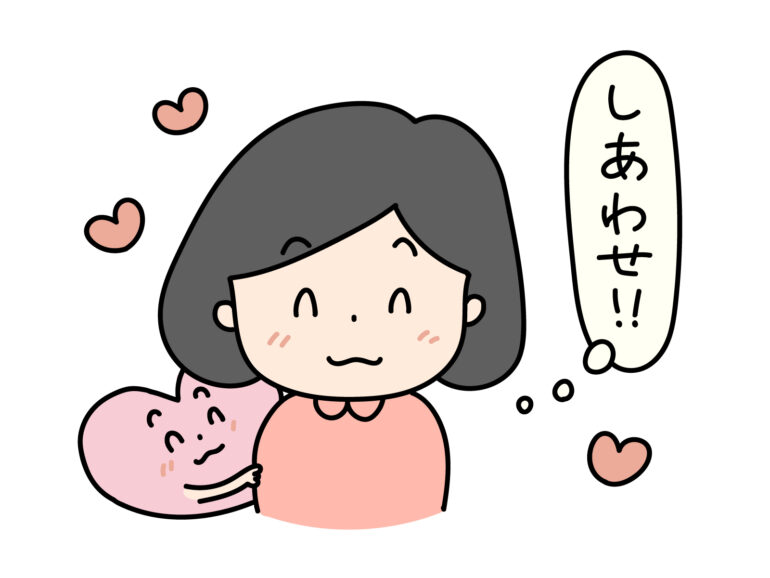私は普段、「アダルトチルドレン(AC)」や「HSP」などの生きづらさを感じている方達向けのカウンセリングをしているので、今回はそのことに関連したお話をしたいと思います。
ずっと私を悩ませてきたことでもある「アダルトチルドレン」の一つの症状についてのお話です。
どうして幸せを素直に感じられないの?
「楽しいことがあっても素直に楽しめなかったり、不安になったりする」
「幸せを感じることにどこか罪悪感がある」

—こんな気持ちを抱いたことはありませんか?
本来なら嬉しいはずの瞬間に、なぜか素直に受け入れられなかったり、
純粋に楽しめなかったりする・・・実は私もずっとそうでした。
もしかすると、それはあなたの過去の経験が影響しているかもしれません。
特に、幼少期に周りの期待に応えることを優先してきた人は
「幸せになることが怖い」
「自分(だけ)が幸せになってはいけない」
と感じることが多いのです。
これは、アダルトチルドレンの特徴のひとつでもありです。
アダルトチルドレン(AC)とは?
子どもの頃に家庭環境の影響を受け、大人になっても生きづらさを感じている人のこと。
親の期待に応えることを優先しすぎた結果、自分の気持ちを素直に表現することができなくなることがあり、幸せを感じることに抵抗を持ってしまうのです。
特に、「自分が幸せになると誰かが苦しむのではないか」という罪悪感が根付いてしまうと、楽しいことがあっても心から楽しめなくなってしまいます。
幸せになれる人、なれない人の違いは?
幸せになれる人となれない人の違いは、「自分の素直な感情を認められるかどうか」です。幸せを自然に感じられる人は、どんな感情も「これは自分の気持ち」と素直に受け止めています。

一方、幸せになれないと感じる人は、
「こんな気持ちを持ってはいけない」
「楽しいことを感じるのが怖い」と、
自分の気持ちを無意識のうちに否定してしまう傾向があります。
この習慣を変えることで、幸せを感じることへの抵抗を減らすことができます。
自分の感情を認めるとは?
まずは、「どんな気持ちもあっていい」と自分に許可を出すことが大切です。
幸せを感じることに抵抗がある人ほど、「自分の気持ちを認めること」に違和感を覚えるかもしれません。
しかし、小さなことから始めてみることで、その感覚は少しずつ変わっていきます。
例えば、
🍀美味しい食べ物を食べたときに「美味しい」と思ったら、その気持ちを否定せずに受け入れる。
🍀リラックスできる時間を持てたら「私は今、安心している」と認めてみる。
などです。
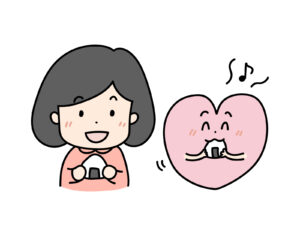
こうして自分の感情を認めることを積み重ねていくことが、「幸せを感じても大丈夫なんだ」という感覚を育てるための第一歩になります。
アダルトチルドレン
”Aさん”の変化
アダルトチルドレンの傾向があったクライアントのAさん(男性)から、ある日こんな相談がありました。
「幸せを感じると不安になる」
具体的に聞いていくと、
「何かに対して”楽しい”と感じた瞬間に罪悪感が出てきて、ふと現実に戻される感覚になる。」
「幸せだと感じることがあると、どうせこの幸せは続かない…と考えてしまうので、
何もかも心から楽しむことができません。」ということでした。

何もかも心から楽しめないなんて、すごく辛いことですよね。
しかし彼は楽しいことや幸せを感じたときに
今、自分が楽しいと感じていることを否定せず、
自分の感情に対して素直に「楽しいよね」「幸せだね」と認めてあげる練習を始めました。
始めた当初は違和感や気恥ずかしさがあったようですが、
自分の素直な感情を認めることで、少しずつ「楽しんでもいいんだ」「喜んでもいいんだ」と素直に感じることができるようになっていきました。

素直な気持ちを大切にする
今回は、「幸せになれる人、なれない人」について書かせていただきました。
せっかく楽しいことや幸せなことがあっても、感情に素直になれない状態だと、
「幸せになっている」とは思えないですよね。
幸せを感じることに抵抗がある人は「自分の気持ちを認める練習」をすることで、その抵抗を少しずつ減らすことができます。
どんな気持ちも「これは自分のもの」と受け止めることで、心が軽くなります。
あなたが安心して幸せを感じられるようになるために、「今の気持ちを認める練習」を始めてみませんか。
--進藤いちか🍀のカウンセリング--
イメージワークを続けても気持ちが晴れないと感じたり、不安や悩みが強くて日常生活に影響が出る場合は、カウンセリングを頼ってくださいね。
無理せず、あなたに合った方法で心を整えるお手伝いをさせていただきます。